【行政書士が解説】建設業許可「財産的基礎」要件を徹底解説!500万円の自己資本がない場合の対策も
こんにちは。
大阪府茨木市のアルバトロス行政書士事務所です。
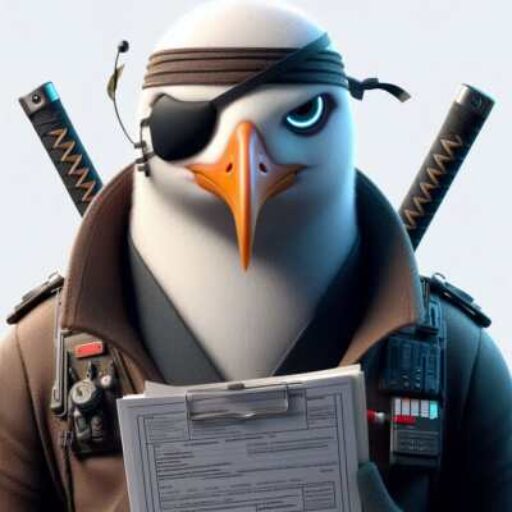
「建設業許可を取りたいけど、500万円の自己資本がないとダメって本当?」
「ウチは赤字決算なんだけど、許可は無理かな…」
そんな風に悩んでいませんか?
建設業許可の要件の中でも、特に多くの経営者の方が頭を悩ませるのが、この「財産的基礎」です。
事業を安定して運営する能力があるかを示す重要な指標ですが、その基準や満たし方が分かりにくいと感じている方も少なくありません。
この記事では、建設業許可の「財産的基礎」について、一般建設業と特定建設業に分けて、それぞれの要件をわかりやすく解説します。さらに、もし要件を満たせない場合でも、どうすればクリアできるのか、具体的な対策までご紹介します。
ぜひこの記事を読んで、許可取得に向けた第一歩を踏み出してください。
一般建設業許可の財産的基礎
一般建設業許可の場合、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- これは、貸借対照表の純資産の部に記載されている金額です。法人であれば株主資本等変動計算書の純資産合計額、個人事業主であれば期首資本金に事業主借・事業主貸を反映した金額です。この基準が最も一般的で、多くの中小企業がこの方法で要件を満たします。
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 金融機関から発行される「預金残高証明書」で証明します。申請時、直前1か月以内の日付で発行された預金残高証明書の残高が500万円以上であることが必要です。資金調達能力を示すため、証明書の日付から申請までの間に残高が大きく変動していないか確認されます
特定建設業許可の財産的基礎
特定建設業許可は、元請として1件の工事につき4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請けに出す場合に必要となります。
このため、一般建設業よりも厳しい基準が設けられています。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)}÷資本金×100上記計算式により算出された数字が20以下であれば問題ありません。繰越利益剰余金に負の額がない場合は計算するまでもなく欠損比率の要件をクリアしています。
- 流動比率が75%以上であること
- 流動比率(流動資産 ÷ 流動負債 × 100)は、短期的な支払い能力を示す重要な指標です。この比率が高いほど、短期的な負債を返済する能力が高いと判断されます。75%という基準は、短期的な資金繰りの安定性を測るためのものです。
- 資本金が2,000万円以上、かつ自己資本が4,000万円以上であること
- 特定建設業許可では、工事の規模が大きくなるため、より強固な財務基盤が求められます。資本金と自己資本の両方で基準を満たす必要があります。自己資本は、負債を差し引いた純粋な資産であり、企業の財務的な安定性を示す最も重要な指標の一つです。
これらの要件は、建設工事の規模や責任の大きさに応じて設定されており、事業者が責任を持って工事を完成させられるだけの資金力を持っているかを客観的に判断する基準となります。
自己資本が不足している場合の対策
自己資本が500万円に満たない場合でも、許可を諦める必要はありません。以下の方法で財産的基礎の要件を満たすことが可能です。
- 増資を行う
- 資本金を増やすことで、自己資本を500万円以上にする方法です。株主からの出資や、事業主からの追加出資によって行われます。
- 借入金で補填する
- 金融機関から500万円以上を借り入れることで、預金残高を増やす方法です。ただし、借入金は返済義務があるため、計画的な返済が求められます。
- 資産を売却する
- 事業に使用していない不動産や車両などを売却し、現金化することで自己資本を増やす方法です。
- 親族から借入を行う
- 親族からの借入金も、自己資本を増やす方法として有効です。ただし、借用書を作成するなど、正式な手続きを踏む必要があります。
まとめ
建設業許可の財産的基礎は、事業の健全性を証明するための重要な要件です。
一般建設業では500万円以上の自己資本または資金調達能力が、特定建設業ではより厳しい財務指標が求められます。
これらの要件をクリアすることで、事業者は安定した経営基盤を持ち、責任ある工事を遂行できると認められます。
許可申請にあたっては、自社の財務状況を正確に把握し、必要に応じて増資や借入など適切な対策を講じることが成功への鍵となります。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
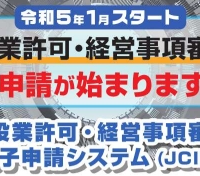
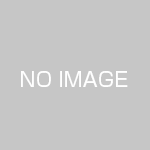


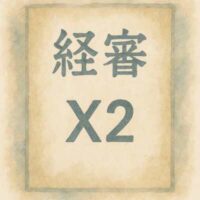
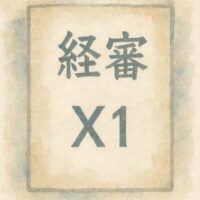

この記事へのコメントはありません。