塗装工事業で建設業許可取得!行政書士が徹底解説する申請の全手順と注意点
塗装工事業の建設業許可を徹底解説!申請のポイントを解説
こんにちは。
大阪府茨木市のアルバトロス行政書士事務所です。
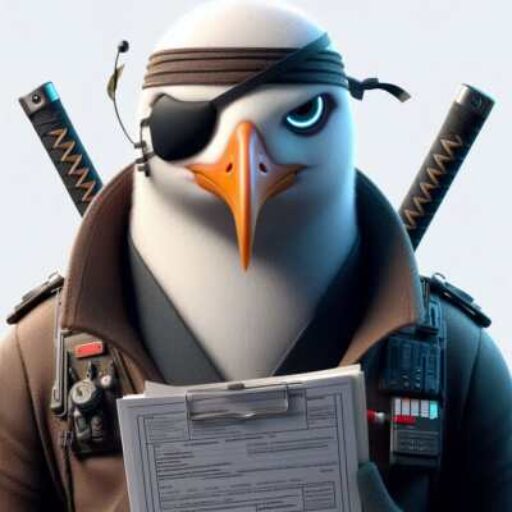
行政書士として建設業許可申請に携わる中で、特にご相談の多い業種の一つが塗装工事業です。
この記事では、塗装工事業の建設業許可を取得するための要件、申請の流れ、
そして見落としがちな注意点まで、専門家の視点から徹底的に解説します。
これから許可取得を目指す事業者の方々が迷うことなく申請を進められるよう、詳細かつ実践的な情報を提供します。
短い記事になってますので最後までお付き合いください。
建設業許可とは?なぜ塗装工事業に必要か
建設業許可とは、建設工事を請け負うために必要な許可です。
建設業法に基づき、一定規模以上の工事を請け負う場合に義務付けられています。
具体的には、1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必須となります。
この金額は、材料費込みの金額であり、元請・下請を問わず適用されます。
塗装工事業を営む皆様の中には
「うちは小規模な工事しかやらないから関係ない」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、現在の建設業界では
元請業者から下請業者への指導が強化されており
元請が請け負う工事全体で許可が必要な規模の場合、
下請業者も許可を持っていることが求められるケースが増えています。
また、将来的に事業を拡大していく上で
より大規模な工事や公共工事への参入を視野に入れるのであれば
建設業許可は不可欠な「パスポート」となるでしょう。
塗装工事業とは?建設業法上の定義と工事内容
建設業許可において「塗装工事業」は、建設業法別表第一に掲げられている29の業種のうちの一つです。
その内容は、以下の工事を指します。
「塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事」
具体的には、以下のような工事が塗装工事業に該当します。
・建築物、橋梁、構造物等の塗装工事全般 ・路面標示設置工事(ライン引きなど) ・溶射工事(金属溶射など) ・ライニング工事(防食、防水などを目的とした内面塗装) ・布張り仕上工事(壁紙張りは内装仕上工事に分類されるため、注意が必要です) ・鋼構造物塗装工事 ・木材塗装工事 ・建築物等における吹付けアスベスト除去工事(塗装を伴う場合)
よく混同されがちなのが、防水工事です。
アスファルト防水、シート防水などは防水工事業に分類されます。
しかし、建物の屋上や外壁に塗料を塗布して防水効果を持たせる「塗膜防水」は
塗装工事業と防水工事業のどちらにも該当し得ます。
工事内容によって判断が分かれるため、不明な場合は専門家にご相談ください。
塗装工事業の建設業許可を取得するための5つの要件
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた5つの要件をすべて満たす必要があります。
これらの要件は、建設業を適正に営むための経営能力と施工能力を担保するためのものです。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の設置
建設業の経営を適切に行うための責任者です。
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は本人または支配人であることが求められます。
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 例:塗装工事業を営む会社の代表取締役として5年以上経営に携わった経験 ・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ・許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐する経験を有する者 例:財務、経理、労務管理など、経営判断に直接関与しないものの、経営を実質的に支える業務経験 ・5年以上常勤役員等としての経験+建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者で、経管を直接補佐する者として、財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの経験を5年以上有する者を置く場合
この要件を満たすためには、経験期間の証明が非常に重要になります。
役員変更履歴事項証明書、確定申告書、工事請負契約書、請求書など、客観的な資料を揃える必要があります。
2. 営業所技術者(改正前の専任技術者)の設置
建設工事の施工に関する技術的な責任者です。
営業所ごとに常勤で配置し、その営業所で請け負う建設工事について、適切な施工を確保する能力が必要です。
塗装工事業の営業所技術者となるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
ア. 国家資格
以下のいずれかの資格を有する者。
・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・1級土木施工管理技士 ・2級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・技能検定1・2級『塗装・木工塗装・木工塗装工』 ・技能検定1・2級『建築塗装・建築塗装工』 ・技能検定1・2級『金属塗装・金属塗装工』 ・技能検定1・2級『噴霧塗装』 ・技能検定1・2級『路面標示施工』 *2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要です
イ. 実務経験
「指定学科卒業の場合」 ・高校、専門学校卒業後、5年以上の実務経験 ・大学、高等専門学校卒業後、3年以上の実務経験 (指定学科:土木工学、建築学、)
「指定学科以外卒業の場合」 ・10年以上の実務経験
実務経験は、単に工事に携わった期間ではなく、「許可を受けようとする建設業種の工事の実務経験」である必要があります。
塗装工事であれば、塗装工事の請負契約書、注文書、請求書、などが証明資料となります。
3. 誠実性
建設業法に違反する行為や、不正な行為を行うおそれがないことを指します。
具体的には、以下のいずれかに該当しないことが求められます。
・不正または不誠実な行為をするおそれがある場合(例:詐欺、脅迫、横領などの罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者) ・建設業法に違反して営業停止処分を受け、その期間が満了していない者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反する者
役員だけでなく、支店長や営業所長など、実質的に経営を支配している者も対象となります。
4. 財産的基礎または金銭的信用
建設工事を請け負う上で必要な資金力があることを示す要件です。
「自己資本が500万円以上であること」 法人の場合は貸借対照表の純資産の部、個人の場合は期首資本金で判断します。 「または500万円以上の資金調達能力があること」 金融機関の発行する預金残高証明書などで証明します。 新規設立の法人など、自己資本が500万円に満たない場合は、口座に500万円以上の残高があることを証明できれば要件を満たします。
直前決算の財務状況が非常に重要になります。
赤字決算や債務超過の場合でも、資金調達能力を示すことで要件を満たせる可能性がありますが、早めに専門家にご相談いただくことをお勧めします。
5. 欠格要件に該当しないこと
上記4つの要件を満たしていても、以下のいずれかの「欠格要件」に該当する場合は、許可を受けることができません。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ・許可の取り消し処分を受けて5年を経過しない者 ・暴力団員等
これらの要件は、申請者だけでなく、役員、実質的な支配者など、許可を受けようとする事業者に関わる全ての人に適用されます。
申請の流れと必要書類
建設業許可の申請は、多くの書類と手順を要します。
ここでは一般的な流れと主要な必要書類について説明します。
申請の流れ
- 要件の確認と資料収集:まずは上記の5つの要件を満たしているか確認し、それを証明する書類を収集します。これが最も時間と手間のかかるプロセスです。
- 申請書類の作成:申請書本体に加え、添付書類を漏れなく作成します。書式は各都道府県の建設業担当部署のウェブサイトで確認できます。
- 申請書の提出:申請先の窓口に提出します。原則として郵送での申請はできません。窓口での形式審査が行われます。
- 審査:提出された書類に基づき、要件を満たしているかどうかの実質審査が行われます。必要に応じて追加資料の提出や質疑応答があります。
- 許可通知:審査をクリアすれば、許可通知書が交付されます。
主要な必要書類(一部抜粋)
・建設業許可申請書 ・役員等の一覧表 ・経営業務の管理責任者の確認資料(経験を証明する書類) ・専任技術者の確認資料(資格証、実務経験証明書、工事経歴書など) ・直近の財務諸表(貸借対照表、損益計算書など) ・納税証明書 ・身分証明書、登記されていないことの証明書(役員全員分) ・営業所の写真、案内図 ・定款(法人の場合) ・履歴事項全部証明書(法人の場合) ・印鑑証明書
これらの書類はあくまで一部であり、
各都道府県や申請する許可の種類(新規、更新など)によって追加で必要となる書類があります。
特に、経営業務の管理責任者と営業所技術者の経験を証明する書類は、非常に厳しく審査されます。
過去の契約書や請求書、工事台帳などを日頃から整理しておくことが重要です。
許可取得後の義務と注意点
建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。許可を取得した後も、いくつかの重要な義務と注意点があります。
1. 毎年の事業年度終了届の提出
毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に、その年度の工事経歴や財務状況などを記載した「事業年度終了届」を提出する義務があります。
これを怠ると、許可の更新ができなくなる可能性があります。
2. 変更届の提出
経営業務の管理責任者や専任技術者の変更、役員の変更、営業所の所在地変更など、許可申請時に届け出た事項に変更があった場合は、30日以内に「変更届」を提出する必要があります。
特に、重要な役職の変更は速やかに届け出る必要があります。
3. 5年ごとの更新申請
建設業許可の有効期間は5年間です。
有効期間満了日の30日前までには更新申請を行う必要があります。
更新申請を忘れると、せっかく取得した許可が失効してしまい、再度新規申請を行うことになります。
4. 適切な帳簿の備え付け
建設業法では、請け負った建設工事に関する帳簿(請負契約に関する帳簿、施工体系図など)を備え付けることが義務付けられています。
5. 一括下請負の禁止
建設工事の一括下請負(丸投げ)は、原則として禁止されています。
特別な場合を除き、元請が工事の大部分を他の業者に一括して請け負わせることはできません。
6. 適正な施工体制の確保
下請業者との契約、安全管理、品質管理など、適正な施工体制を確保する責任があります。
専門家である行政書士に依頼するメリット
建設業許可の申請は
多岐にわたる要件の確認、膨大な量の書類作成、そして行政庁との折衝など
非常に複雑で時間と手間を要します。
特に、普段の業務で忙しい事業者様にとっては、大きな負担となるでしょう。
・正確な要件判断とアドバイス:お客様の状況をヒアリングし、どの要件を満たしているか、何が不足しているかを正確に判断し、適切なアドバイスを提供します。 ・効率的な資料収集と作成:必要書類のリストアップから収集のアドバイス、さらには書類作成までを一貫してサポートします。お客様は事業に専念できます。 ・煩雑な手続きの代行:行政庁との事前相談、申請書の提出、追加資料の提出など、すべての手続きを代行します。 ・不許可リスクの低減:専門家が申請することで、書類の不備や要件の誤認による不許可のリスクを大幅に低減できます。 ・迅速な許可取得:手続きをスムーズに進めることで、より迅速な許可取得が期待できます。
塗装工事業の皆様が、安心して事業を継続・拡大できるよう、建設業許可取得のサポートを通じて貢献できることを願っています。
まとめ
塗装工事業の建設業許可は、事業の発展に不可欠なものです。
500万円以上の工事を請け負う場合
または将来的な事業展開を考慮するならば、許可取得は必須のステップとなります。
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件、財産的基礎、そして誠実性や欠格要件など
クリアすべきハードルは少なくありません。
しかし、一つ一つの要件を丁寧に確認し、必要な書類を漏れなく揃えることで必ず許可は取得できます。
この記事が、塗装工事業を営む皆様の建設業許可取得の一助となれば幸いです。
ご不明な点や具体的なご相談がございましたら、お気軽にご相談ください。
皆様の事業の発展を力強くサポートいたします。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。




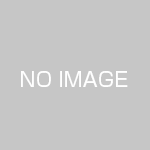
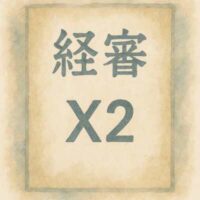
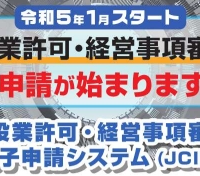

この記事へのコメントはありません。