【行政書士解説】建設業許可に必要な「身分証明書」を解説!取得方法から注意点まで

こんにちは。大阪府茨木市のアルバトロス行政書士事務所です。
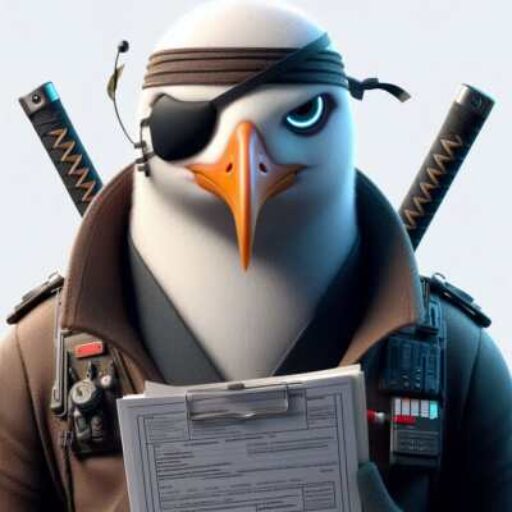
身分証明書は、主に「本籍地の市区町村で取得する身分証明書」が該当します。
この記事では、この書類の具体的な内容、取得方法、そして注意点について詳しく解説していきます。
短い記事なので最後までお付き合いください。
建設業許可申請における身分証明書とは?~必要書類と取得方法を徹底解説~
1.なぜ身分証明書が必要なのか?~許可要件との関係~
建設業許可には、欠格要件というものが設けられています。これは、過去に一定の罪を犯した者や、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者など、建設業を営む上で不適格とされる人物に対して許可を与えないための規定です。
身分証明書は、これらの欠格要件に該当しないことを公的に証明するための重要な書類となります。
具体的には、以下の欠格要件に該当しないことを確認するために「身分証明書」が使用されます。
- 成年被後見人または被保佐人でないこと(破産者で復権を得ていない者を含む)
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
- 破産宣言又は破産手続き開始決定の通知をうけていないこと
2.本籍地の市区町村で取得する「身分証明書」
建設業許可申請で求められる身分証明書は、本籍地の市区町村役場で取得するものです。これは、一般的に「身分証明書」という名称で発行されますが、運転免許証やマイナンバーカードとは全く異なる、特定の情報を証明する公的書類です。
(1) 「身分証明書」で証明される内容
この身分証明書には、以下の3つの項目が記載されています。
これらの項目は、建設業許可の欠格要件に直接関係する内容です。
- 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
禁治産と準禁治産は、成年後見制度の前身として存在していた「禁治産又は準禁治産制度」という制度の中で設けられていた被補助者の名称で、それぞれ今でいう成年被後見人と被保佐人にあたります。
つまり成年後見制度が開始された平成21年4月1日より以前に、成年被後見人や被保佐人に該当する人物でなかったことの証明は、この「禁治産又は準禁治産の宣告の通知をうけていないこと」により証明することになります。
なお、この「禁治産又は準禁治産制度」では禁治産や準禁治産を戸籍上で管理していた為、その名残で戸籍の一種である身分証明書に、後見の登記有無が記載されています。 - 後見(こうけん)の登記の通知を受けていないこと: 上記と同様に、成年後見制度における被後見人ではないことを証明します。
- 破産手続開始の決定の通知を受けていないこと: 自己破産などの手続きを行い、破産者として復権(債務を免除され、法律上の制限がなくなること)を得ていない状態ではないことを証明します。
これらの項目が「ない」ことを公的に証明することで、申請者が建設業を営む上で支障のない、適格な人物であることを示します。
特に、経済的な信用や判断能力に関する事項は、建設工事を適切に実施するための基礎的な要件となります。
(2) 取得方法
この身分証明書は、以下の手順で取得します。
- 取得場所: 本人の本籍地がある市区町村役場の窓口。現住所の役場では取得できない点に注意が必要です。本籍地が現住所と異なる場合は、間違えないようにしましょう。
- 必要なもの:
- 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの公的証明書。
- 手数料:市区町村によって異なりますが、一般的に1通あたり300円程度です。現金で用意しておきましょう。
- (代理人が申請する場合)委任状:本人以外が申請する場合は、本人が作成した委任状と、代理人の本人確認書類が必要です。
- 郵送での請求: 本籍地が遠方にあるなど、窓口に行くことが難しい場合は、郵送で請求することも可能です。
- 各市区町村のウェブサイトから「身分証明書交付請求書」をダウンロードし、必要事項を記入します。
- 本人確認書類のコピー(健康保険証のコピーを同封する場合は、保険者番号や記号・番号を塗りつぶすなど、個人情報保護に配慮してください)。
- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)。
- 返信用封筒(切手を貼り、宛名を記入したもの)。 これらの書類を同封し、本籍地の市区町村役場戸籍課宛に郵送します。郵送の場合、発行から到着までに時間がかかるため、申請時期に余裕をもって手続きを行いましょう。
(3) 取得上の注意点
- 有効期限:建設業許可申請において、身分証明書は発行から概ね3ヶ月以内のものが求められます。取得したら速やかに申請手続きを進めるようにしましょう。有効期限を過ぎたものは再取得が必要です。
- 申請者の範囲:個人事業主の場合は事業主本人のもの、法人の場合は役員全員(監査役を含む)および支配人(もしいる場合)の身分証明書が必要となります。また、令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長など、契約締結権限を持つ者)がいる場合も、その者の身分証明書が必要です。
3.まとめ
本籍地の市区町村で取得する身分証明書は、欠格要件に該当しないことを示す公的な証明となります。
取得場所が本籍地であること、有効期限があること、そして申請者となるすべての関係者の分が必要であることなど、いくつかの注意点があります。これらのポイントをしっかりと押さえ、不備のないスムーズな許可申請を目指しましょう。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

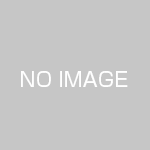

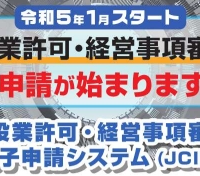


この記事へのコメントはありません。