【要確認】本当に必要なのは「建築一式工事」?許可申請前に考えるべき注意点
- 取扱業務, 建設業許可
- 大阪府 建設業許可 行政書士, 建築一式工事 注意, 茨木市 建設業許可 行政書士
- コメント: 0
こんにちは。
大阪府茨木市のアルバトロス行政書士事務所です。
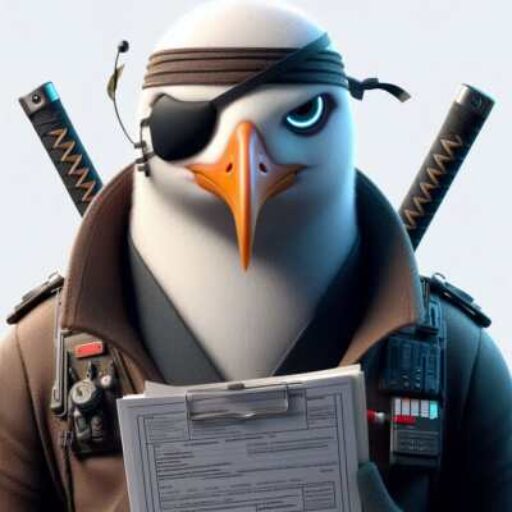
「新築工事もリフォーム工事も、建築に関する仕事なら『建築一式工事』の許可があれば大丈夫だろう」
そうお考えではありませんか?
もしそうなら、少し立ち止まって考えてみてください。
建設業許可は29の業種に分かれていますが、その中でも特に誤解されやすいのが「建築一式工事」です。
この許可があれば「何でも請け負える」と安易に考えてしまうと、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。
事業に必要なのは本当に建築一式工事でしょうか?
この記事では、行政書士の視点から、「建築一式工事」と「専門工事」の違い、
そして適切な許可業種を選ぶために確認すべきポイントを解説します。
長くないので気軽に読んでください。
Table of Contents
Toggle大阪府の建設業許可手引きはこちら
1. 建築一式工事の「定義」と「請け負える範囲」を正しく理解しましょう
建設業許可は29業種に分かれており、それぞれ請け負える工事の範囲が定められています。
その中でも「建築一式工事」は、他の専門工事とは明確に異なる定義があります。
建築一式工事とは
建築一式工事は、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」です。
簡単に言えば、複数の専門工事業者(下請け)を統括し、建築物全体を完成させる元請け工事を指します。
戸建住宅やビルの新築工事がこれに該当します。

建築一式工事だけでは「何でもできる」わけではない
重要な点として、建築一式工事の許可を取得しても、すべての専門工事を無制限に請け負えるわけではありません。
建設業許可は、原則として請負金額が500万円(税込)を超える工事に対して必要となります。
この「500万円」という金額は、専門工事においても適用される基準です。
もし建築一式工事の許可しか持っていない場合、
請負金額が500万円を超える専門工事を単独で請け負うことはできません。
例えば、建築一式工事の許可を持つ事業者が、
請負金額が800万円の「内装仕上工事」だけを請け負う場合、これは「無許可工事」となります。
建築一式工事の許可は、「建築物全体の建設」に対してのみ有効であり、
特定の専門工事には個別の許可が必要となる場合があるのです。

2. 専門工事との「違い」と「混同のリスク」を認識する
建築一式工事と専門工事の違いを混同すると、思わぬリスクが生じます。
専門工事とは
専門工事は、特定の技術や技能を必要とする27の工事を指します(例:大工工事、電気工事、管工事、内装仕上工事など)。
専門工事は、元請けだけでなく、下請けとして特定の工事を専門に行う場合に許可が必要です。
混同のリスク
建築一式工事の許可しかないのに、専門工事を単独で請け負うと「無許可工事」とみなされる可能性があります。
例えば、大規模なリフォーム工事を請け負う場合、
それが「総合的な企画、調整」のもとに行われるのであれば建築一式工事に該当しますが、
単に屋根の修繕だけを行う場合は「屋根工事」の専門工事に該当します。
事業内容を正確に把握し、最適な許可業種を選択しなければ、行政指導や罰則の対象となるリスクがあるのです。
3. 「許可要件」と「事業計画」を照らし合わせる
建築一式工事の許可は、専門工事と比較してより高度な要件が求められる場合があります。
特に、「営業所技術者」の要件は慎重に確認する必要があります。
営業所技術者の要件
建築一式工事の専任技術者は、以下のいずれかの資格や実務経験が必要です。
・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(建築) ・一級建築士 ・二級建築士
これらの資格がない場合、特定の要件を満たす実務経験(例:指定学科卒業後3年、それ以外は10年など)が必要となります。
事業計画との照合
もし、将来的に専門工事を主力事業として展開する計画があるのであれば、
建築一式工事の許可だけでなく、関連する専門工事の許可も取得することを検討すべきです。
例えば、「戸建住宅の新築」と「電気設備工事」の両方を手掛けるのであれば、
建築一式工事と電気工事の両方の許可取得が必要です。
また、許可取得後の経営体制(特に営業所技術者の配置)を維持できるかも重要な検討事項です。
事業計画と許可要件を照らし合わせ、無理のない形で許可を取得することが重要です。
まとめ
建築一式工事の許可は、大規模な新築工事などを手掛ける上で不可欠ですが、
その定義と請負範囲を正しく理解することが重要です。
「建築一式」と「専門工事」を混同せず、ご自身の事業内容に最適な許可業種を選択することで、
法令を遵守し、スムーズな事業運営が可能となります。
許可取得に関するご不明な点や、事業内容に応じた最適な許可業種のご相談はぜひ当事務所にご相談ください。
関連記事
コメント
この記事へのトラックバックはありません。




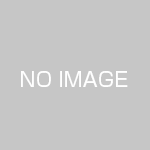
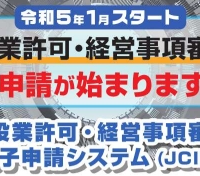


この記事へのコメントはありません。