「まさか無許可で運んでない?」建設産廃8種と許可の落とし穴
こんにちは。
大阪府茨木市のアルバトロス行政書士事務所です。
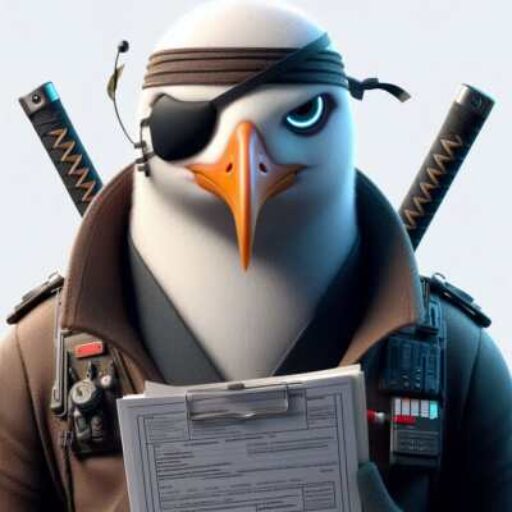
建設工事に伴って発生する廃棄物はその種類や量によって許可の要否や手続きが大きく異なります。
建設業者様にとって基本的な品目になるのが「建設系産廃8種」です。
この記事では「建設系産廃8種」の詳細と、許可取得のための具体的なステップを解説していきます。
短い記事なので最後までお付き合いください。
1. 建設産廃8種:各品目の定義
- 木くず
- 定義: 建設工事から発生する木材や木片。建築物の解体工事で発生する木材、型枠工事で出る端材、内装工事で出る廃材などが該当します。
- 見極め方: 単なる燃やすための薪や家庭から出る一般廃棄物とは異なり、事業活動(建設工事)に伴って排出されたものに限られます。例えば、内装リフォームで出た廃畳も、この品目に含まれます。
- 繊維くず
- 定義: 建設工事から発生する天然繊維くずが主。具体的には、建築物の内装材として使われたじゅうたんや壁紙(クロス)、畳の芯材などが該当します。
- 見極め方: 産業廃棄物としての繊維くずは、事業活動から発生したものに限定されます。ビニールクロスなど、化学繊維が主成分の場合は「廃プラスチック類」に分類されることもあり、注意が必要です。
- がれき類
- 定義: 工作物の新築、改築、除去により生じたコンクリートの破片、アスファルトの破片その他これらに類する不要物。アスファルトコンクリート塊やコンクリート塊が代表的です。
- 見極め方: 「がれき類」と「ガラスくず、コンクリートくず(がれき類を除く)、陶磁器くず」との違いが重要です。がれき類は主に工作物の除去から生じるものを指し、建築資材として使われていた状態のものが該当します。
- 金属くず
- 定義: 鉄骨、鉄筋、足場材などの金属類、また、アルミサッシや配管、銅線など、多岐にわたります。
- 見極め方: 工事現場で発生する金属全般が対象です。ただし、廃家電製品など、産業廃棄物として別途定められているものは、その品目に分類される場合があります。
- ガラスくず、コンクリートくず(がれき類を除く)、陶磁器くず
- 定義: がれき類と区別されるのがポイントです。窓ガラスやタイル、衛生陶器(便器など)、レンガなどが該当します。
- 見極め方: 「がれき類」が構造物の一部だったのに対し、こちらは構造物そのものではなく、その付属物や内装材として使われたものが主な対象となります。
- 廃プラスチック類
- 定義: 建設現場で発生する様々なプラスチック製品。塩ビ管やビニールシート、断熱材(発泡スチロール)、養生材などが含まれます。
- 見極め方: 建設現場で出るプラスチック類は、ほとんどがこの品目に該当します。複数の素材が混ざっている場合は、主要な素材がプラスチックであれば、この品目として扱うのが一般的です。
- 紙くず
- 定義: 建設工事から発生するダンボール、紙製の養生材、廃書類などが該当します。
- 見極め方: 事務作業で出る一般的な紙ごみとは異なり、建設工事という事業活動に直接関連して排出されたものに限られます。
- ゴムくず
- 定義: 石膏ボードやゴムくずなど、建設現場で一般的に発生する品目を指します。
- 見極め方: この「その他」の扱いが許可申請の重要なポイントとなります。多くの場合、許可申請時にこれらの品目を明記し、許可を取得することで、合法的な運搬が可能となります。
これらの産業廃棄物は、「建設系廃棄物8品目」と呼ばれており、以上の8品目に、必要に応じて「汚泥」「廃アルカリ」等の品目を加えることもあります。
2. 許可取得へのロードマップ
- 要件の確認:許可の取得資格
- 講習会の受講: 収集運搬業の許可申請には、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。
- 財産的基礎: 事業を安定して継続できるだけの資金力があることを証明する必要があります。具体的には、直近3年間の貸借対照表や、金融機関の残高証明書などが求められます。
- 欠格要件に該当しないこと: 過去に廃棄物処理法違反などの処分を受けていないかなど、法的に事業を行う上で問題がないかを確認します。
- 書類作成と申請手続きのポイント
- 事業計画書の作成: どのような廃棄物を、どの車両で、どのように運搬するのかを具体的に記載します。
- 車両や積替保管施設の明記: 運搬に使う車両の詳細(車検証、写真など)を提出します。
- 申請先の確認: 運搬を行う都道府県や政令指定都市ごとに許可が必要です。事業範囲に応じて、複数の自治体への申請が必要となる場合があります。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

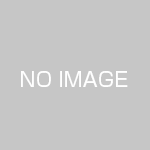




この記事へのコメントはありません。