建設業許可は、建設工事を請け負う上で非常に重要な許可です。
500万円以上の内装仕上げ工事を請け負う場合、法律で義務付けられています。
500万円未満の工事であっても、将来的に事業を拡大していくことを考えると、早めに取得しておくことをおすすめします。
許可を持っていることで、以下のようなメリットがあります。
・大きな仕事を受注できる:公共工事や大手ゼネコンからの仕事は、ほとんどの場合、建設業許可が必須です。 ・顧客からの信頼度アップ:許可を持っていることで、安心して工事を任せてもらえるようになります。 ・下請け業者としての信頼度アップ:元請け業者からの評価も高まります。
この記事では、内装仕上げ工事業で建設業許可を取得したいと考えている方のために、
専門用語を極力避けながら、分かりやすく、そして徹底的に解説していきます。
「建設業許可なんて難しそう…」と感じている方もご安心ください。
一つ一つ丁寧に解説していきますので、この記事を読み終わる頃には、
内装仕上げ工事の建設業許可申請の流れがしっかり理解できるようになっているはずです。
Table of Contents
Toggle内装仕上げ工事とは?建設業許可の「業種」を知ろう
建設業許可には、全部で29種類の「業種」があります。
内装仕上げ工事の場合、その名の通り「内装仕上工事」という業種に該当します。
内装仕上工事には、具体的にどのような工事が含まれるのでしょうか?
いくつか例を挙げてみます。
・内装間仕切工事:部屋を区切る壁の設置など ・天井仕上工事:天井のボード貼りやクロス貼りなど ・壁仕上工事:壁のクロス貼り、塗装、タイル貼りなど ・床仕上工事:フローリング、カーペット、Pタイルなどの床材貼り ・畳工事:畳の設置や交換 ・ふすま工事・障子工事:ふすまや障子の新設・張替え ・家具工事:造作家具の製作・取り付け ・防音工事:吸音材や遮音材の設置 ・内装建具工事:ドアや引き戸などの室内建具の取り付け
このように、建物内部の最終的な仕上げに関わる工事全般が、内装仕上工事の範囲となります。
もし、ご自身の事業内容が上記に当てはまるのであれば、この「内装仕上工事」の許可を目指すことになります。
建設業許可の種類:知っておきたい2つのポイント
建設業許可には、大きく分けて2つの種類があります。
1.知事許可と大臣許可
2.一般建設業と特定建設業
それぞれ、内装仕上げ工事業の場合にどう関係してくるのか、見ていきましょう。
1. 知事許可と大臣許可
・知事許可:営業所が一つの都道府県内だけにある場合に取得します。例えば、大阪府内にしか営業所がない場合は、大阪府知事の許可を受けます。ほとんどの内装仕上げ工事業者さんは、この知事許可を取得することになるでしょう。
・大臣許可:営業所が複数の都道府県にまたがってある場合に取得します。例えば、大阪府と兵庫県の両方に営業所がある場合は、国土交通大臣の許可を受けます。
もし、現時点では大阪府内にしか営業所がなくても、
将来的に事業拡大で他の都道府県にも営業所を出す可能性がある場合は、
その時に大臣許可への切り替えが必要になることがあります。
2. 一般建設業と特定建設業
ここは少し複雑に感じるかもしれませんが、非常に重要なポイントです。
- 一般建設業
・発注者から直接工事を請け負い、かつ下請けに出す金額が4,000万円未満の工事のみを行う場合。
・元請けから工事を請け負い、かつ下請けに出す金額が4,000万円未満の場合。
ほとんどの内装仕上げ工事業者さんは、この一般建設業の許可を取得することになります。
- 特定建設業:
・発注者から直接工事を請け負い、かつ下請けに出す金額が4,000万円以上になる工事を行う場合。
特定建設業は、大規模な工事で多くの下請け業者を使う元請け業者向けの許可です。
内装仕上げ工事業で、いきなり4,000万円以上の下請け契約を結ぶことは稀なので、
まずは一般建設業の許可取得を目指すと考えてください。
もし将来的に事業規模が大きくなり、
下請けに4,000万円以上の工事を出すようになった場合は、特定建設業への切り替えが必要になります。
建設業許可取得の「5つの要件」をクリアしよう!
建設業許可を取得するためには、大きく分けて以下の5つの要件を全て満たしている必要があります。
内装仕上げ工事業でも、この要件は変わりません。
1.経営業務の管理責任者(通称:経管)がいること
2.営業所技術者(旧専任技術者)がいること
3.財産的基礎があること
4.誠実性があること
5.欠格要件に該当しないこと
一つずつ、具体的に見ていきましょう。
1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
これは、会社の経営をしっかり管理できる人がいることを示す要件です。
法人の場合は役員の中に、個人の場合は事業主本人が、以下のいずれかの経験を持っている必要があります。
・許可を受けたい業種(内装仕上工事)に関して、5年以上の経営業務の管理経験があること
・許可を受けたい業種以外の建設業に関して、7年以上の経営業務の管理経験があること
・上記に準ずる経験として認められるもの
多くの場合、社長さんや事業主の方がこの要件を満たすことになります。
過去の会社での役員経験や個人事業主としての経験などが該当します。
この経験は、確定申告書や工事請負契約書などで証明することになります。
2. 営業所技術者(旧専任技術者)がいること
工事現場で技術的な指導や管理を行うことができる専門的な知識と経験を持った人がいることを示す要件です。
この人は、会社の常勤役員または従業員である必要があります。
内装仕上工事の営業所技術者になるための具体的な要件は、以下のいずれかを満たすことです。
(1) 国家資格を持っている場合
以下の国家資格のいずれかを持っている人が専任技術者になれます。
国家資格での証明が一番簡単です。
・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(建築、躯体、仕上げ) ・一級建築士 ・二級建築士 ・技能検定「内装仕上げ施工」(1級または2級で、2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要) ・技能検定「建築大工」(1級または2級で、2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要) ・技能検定「畳製作」(1級または2級で、2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要) ・技能検定「表装」(1級または2級で、2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
(2) 実務経験がある場合
国家資格がない場合でも、以下の実務経験があれば営業所技術者になれます。
証明難易度は非常に高いです。
・許可を受けたい業種(内装仕上工事)に関して、10年以上の実務経験があること
この実務経験は、各自治体によって独自のルールがありますが、工事請負契約書、請求書、通帳の入金履歴などを使って証明します。
単に働いていた期間ではなく、「内装仕上工事」として認められる内容の工事に携わっていたことを具体的に示す必要があります。
3. 財産的基礎(お金の条件)があること
建設業許可を取得するには、ある程度の財産(資金)があることを示す必要があります。一般建設業の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
自己資本が500万円以上あること
・法人の場合は、貸借対照表の「純資産の部」の合計額が500万円以上。 ・個人の場合は、開業資金として用意した預貯金残高が500万円以上。
500万円以上の資金調達能力があること
・金融機関から500万円以上の融資を受けられる証明書など。
多くの場合、直近の決算書(法人の場合)や預金残高証明書(個人の場合)で確認されます。
もし自己資本が500万円に満たない場合は、金融機関から500万円の残高証明書を発行してもらうことでクリアできる場合があります。
4. 誠実性があること
建設業を営む上で、法律に違反したり、不正な行為をしたりしない「誠実さ」があるかどうかの要件です。
具体的には、以下のいずれかに該当しないことが求められます。
・不正な手段で建設業許可を取得しようとしていないか ・建築基準法や建設業法などに違反していないか ・請負契約を誠実に履行しないおそれがないか
これは主に、過去の違反歴や罰金刑の有無などで判断されます。
5. 欠格要件に該当しないこと
以下のいずれかに該当する場合は、建設業許可を取得できません。
・破産手続き開始の決定を受けて、復権を得ていない者
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法などに違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
・未成年者(法定代理人が上記の欠格要件に該当しない場合を除く)
建設業許可申請の流れ:書類準備から許可取得まで
それでは、実際に建設業許可を申請する際の流れを見ていきましょう。
多くの書類を準備する必要があるので、計画的に進めることが大切です。
ステップ1:必要書類の確認と収集
これが最も時間と労力がかかるステップです。
前述した5つの要件を証明するための書類を大量に集める必要があります。
法人の場合(一般的な書類)
・定款:会社の設立時に作成した書類 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書):会社の情報が記載された書類 ・役員全員の住民票、身分証明書、健康保険証のコピー ・経営業務の管理責任者の経験を証明する書類:過去の確定申告書、工事請負契約書、請求書、通帳の写しなど ・営業所技術者の資格を証明する書類:資格者証、卒業証明書、実務経験証明書(工事請負契約書、請求書、通帳の写しなど) ・直近の決算書(貸借対照表、損益計算書など):財産的基礎を証明 ・納税証明書 ・健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況を証明する書類 ・営業所の写真
個人の場合(一般的な書類)
・事業主の住民票、身分証明書、健康保険証のコピー ・経営業務の管理責任者(事業主本人)の経験を証明する書類:過去の確定申告書、工事請負契約書、請求書、通帳の写しなど ・営業所技術者の資格を証明する書類:資格者証、卒業証明書、実務経験証明書(工事請負契約書、請求書、通帳の写しなど) ・預金残高証明書:財産的基礎を証明(500万円以上) ・納税証明書 ・健康保険、国民年金、雇用保険の加入状況を証明する書類 ・営業所の写真
【重要ポイント】
書類の量が多く、中には役所や金融機関で取得する必要があるものもたくさんあります。
また、実務経験の証明は、過去の契約書や請求書を遡って探し出す作業が必要になるため、非常に手間がかかります。
ステップ2:申請書の作成
集めた書類をもとに、建設業許可申請書や各種添付書類を作成します。
これらの書類は非常に専門性が高く、正確に記載する必要があります。
少しでも不備があると、修正を求められたり、申請が不受理になったりして、許可取得が大幅に遅れる原因になります。
【ポイント】
行政書士に依頼すれば、この申請書作成から添付書類のチェックまで、全て任せることができます。
ステップ3:申請手数料の納付
申請書を提出する前に、手数料を納付します。
・知事許可の場合:9万円(申請時) ・大臣許可の場合:15万円(申請時)
これは収入印紙や証紙で納付します。
ステップ4:申請書の提出
作成した申請書と全ての添付書類を、都道府県庁の建設業許可担当部署(大臣許可の場合は国土交通省の窓口)に提出します。
この際、書類に不備がないか、担当者が確認してくれます。
もし不備があれば、その場で修正を求められることもあります。
ステップ5:審査期間
申請書が受理されてから、許可が下りるまでには一定の審査期間があります。
・知事許可の場合:約30日程度 ・大臣許可の場合:約90日程度
この期間中、行政庁から追加で書類の提出を求められたり、内容の確認の連絡が入ったりすることもあります。
ステップ6:許可の取得!
無事に審査が完了すると、建設業許可が下りたことが通知され、許可証が交付されます。
これで、晴れて内装仕上げ工事業として、法律に基づいた建設工事を請け負うことができるようになります。
建設業許可取得後の注意点:維持するためのルール
建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。
許可を維持するためには、いくつかのルールを守る必要があります。
1. 5年ごとの更新
建設業許可には、5年間の有効期限があります。
期限が切れる前に、必ず更新申請を行う必要があります。
更新を忘れてしまうと、せっかく取得した許可が失効してしまい、再度新規申請からやり直すことになってしまいます。
更新申請も、新規申請と同様に書類準備と手続きが必要です。
2. 変更があった場合の届出
許可取得後に、会社や事業の内容に以下のような変更があった場合は、
2週間以内または30日以内に届出をする必要があります。
・役員の変更(追加、辞任など) ・経営業務の管理責任者の変更 ・営業所技術者の変更 ・営業所の名称や所在地変更 ・資本金の変更 ・商号(会社名)の変更
変更届を怠ると、最悪の場合、許可が取り消されてしまう可能性もありますので注意が必要です。
3. 決算変更届の提出
事業年度が終了し、決算が確定したら、4ヶ月以内に決算変更届を提出する必要があります。
決算書を基に建設業法に沿って作成します。
毎年必ず必要な手続きです。
これらの手続きを適切に行うことで、建設業許可を継続的に維持することができます。
決算変更届の詳しい記事はこちらから
内装仕上げ工事業者が建設業許可を取得するメリットを再確認!
ここまで、建設業許可取得の要件や流れについて詳しく見てきました。
改めて、内装仕上げ工事業者さんが建設業許可を取得することの大きなメリットをまとめます。
・ビジネスチャンスの拡大:500万円以上の工事はもちろん、公共工事や大規模な民間工事への参入が可能になります。これまで受注できなかった大きな案件も視野に入ってきます。 ・企業の信頼性向上:許可を持っていること自体が、お客様や取引先、金融機関に対する信頼の証となります。安心して仕事を任せてもらえるようになり、競争力が高まります。 ・社会的な評価の向上:法律を遵守し、適正な事業運営を行っている企業として、社会的な評価も高まります。 ・元請けからの評価アップ:下請けとして仕事を受ける場合でも、建設業許可を持っていることで、元請け業者からの評価が高まり、継続的な取引に繋がりやすくなります。
もし現在、内装仕上げ工事で500万円以上の仕事を請け負っていて、
まだ建設業許可を持っていないのであれば、それは法律違反の状態です。
すぐにでも許可取得に向けて動き出す必要があります。
また、今は500万円未満の工事がメインでも、
将来的に事業を拡大したいと考えているのであれば、
早めに許可を取得しておくことを強くおすすめします。
建設業許可申請は行政書士に任せるのがおすすめ
ここまでお読みいただき、建設業許可申請が非常に多くの書類準備と専門知識を必要とすることをお分かりいただけたかと思います。
・「書類の集め方が分からない」 ・「実務経験の証明方法が難しい」 ・「申請書作成に自信がない」 ・「本業が忙しくて、許可申請に手が回らない」 ・「とにかく早く許可を取りたい」
上記のような悩みをお持ちでしたら、行政書士に依頼することをご検討ください。
複雑な要件の確認から、必要書類のリストアップ、役所への書類請求、実務経験の証明書類の作成、申請書の作成、そして提出まで、
全てのプロセスをトータルでサポートさせていただきます。
専門家である行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
・時間と手間の大幅な削減:ご自身で手続きを行う手間と時間を省き、本業に専念できます。 ・正確かつ迅速な申請:専門知識と経験を活かし、ミスのない申請をサポートします。これにより、許可取得までの期間を短縮できます。 ・安心感:複雑な法律や手続きに関する疑問や不安を解消し、安心して許可取得に臨めます。 ・許可取得後のサポートも充実:更新申請や変更届など、許可取得後の手続きについても継続的にサポートいたします。
内装仕上げ工事業で建設業許可を取得し、事業をさらに発展させたいとお考えでしたら、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
初回のご相談は無料で承っております。
事業がより大きく飛躍できるよう、全力でサポートさせていただきます。
まとめ:建設業許可で内装仕上げの未来を拓く!
内装仕上げ工事業にとって、建設業許可は単なる「義務」ではありません。
それは、事業の信頼性を高め、新たなビジネスチャンスを掴み、将来の成長を加速させるための「投資」と言えるでしょう。
この記事を通じて、建設業許可の重要性、内装仕上工事の業種について、
そして許可取得の5つの要件と具体的な申請の流れについて、ご理解いただけたかと思います。
最初は複雑に感じるかもしれませんが、一つ一つのステップを丁寧に進めていけば許可は取得できます。
建設業許可取得に向けて一歩踏み出したいけれど、何から手をつけていいか分からない、
といった不安があるようでしたら、ご相談ください。
事業の発展を、心より応援しております。
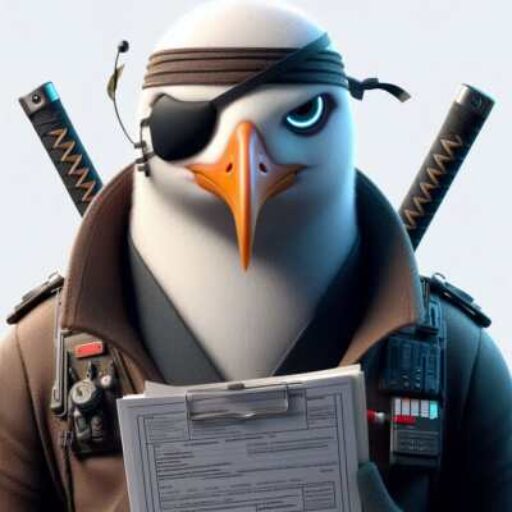



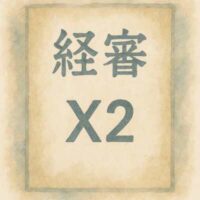
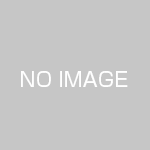

この記事へのコメントはありません。